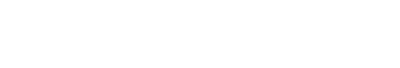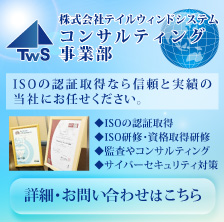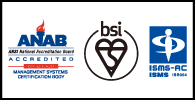3月31日から、NHKの朝の連続テレビ小説「あんぱん」が始まった。この物語は「アンパンマン」の作者、やなせたかしさんとその妻のぶさんの人生を描いている。公式インスタグラムでは、『逆転しない正義を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでを描き、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語』と紹介されている。逆転しない正義とは何かを考え、たまたま所持していた、やなせたかしさんのインタビュー集「なんのために生まれてきたの?」を家で読み返してみた。そこには「逆転しない正義」が語られていた。やなせたかしさんが生きる中で見つけた絶対的な正義、それは「飢えている人を助けること」である。「困っている人、飢えている人に食べ物を差し出す行為は、立場や国に関係なく『正しいこと』。これは絶対的な正義なんです。」と書かれていた。そして、やなせたかしさんは、ひもじい人を助けるヒーローを作ろうと考え、「アンパンマン」を生み出したのである。「アンパンマン」が誰にでも受け入れられ、人気を集めた理由がわかった気がする。正義には時として異なる正義がぶつかり合い、言い争いや戦争に発展することもある。また、立場が変われば正義が逆転することもある。逆転しない絶対的な正義を見つけ出し、それをヒーローにしたやなせたかしさんの偉大さを改めて感じた。