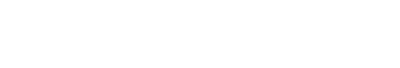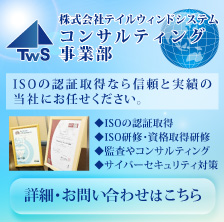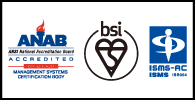先日、初めてズンバというダンスエクササイズに参加した。年齢的にどうかと思ったが、意外にも動け、汗をかく爽快感が心地よく、もっと早く参加すれば良かったと思った。最近は何事にも年齢を言い訳にしがちだが、それでは大きく損をしている。年齢を重ねたからといって何も始められないわけではなく、「まだこれからだ」と前向きに捉え、挑戦する姿勢が大切だ。「こうありたい」「こうなりたい」と目標を持つことが、毎日の充実感とやりがいを生み出し、前向きな姿勢につながる。社内で目標設定のワークショップを行っているが、実際に目標を持ったことで行動や雰囲気が変わった人たちを目の当たりにしてきた。ちょっとした考え方の変化が、1年後、3年後の自分を大きく変えると感じている。小さな目標でも、それを持って行動していきたい。
- 2024/09/25