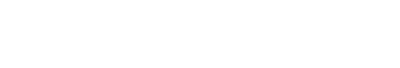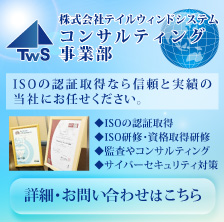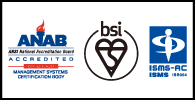以前私は知人から、知識はお金で買えるが教養はお金では買えないと聞いた。知識とは「ある物事を知っていること」であり、教養とは「多くの知識を身につけることで得られる心の豊かさ」である。つまり教養ある人とは、知識が豊富な人格者であり、人に尊敬される人のことだと言える。沢山の知識を身につけ、多くの資格を持つ者が優れた人格者とは限らない。ドイツの哲学者ショーペンハウエルが読書に関して以下の様に言っている。「単に読書をするだけならしない方がましである。人生を考えることに時間を費やした人は、その土地に実際に住んでいたことがある人のようなものだ」なるほどと私は思った。情報は自ら取捨選択し、咀嚼することにより真に自分の栄養となり、初めて教養ある人格者になるのだ。世界はIT化が進むのに何故我々の暮らしはせわしいのだろうか。それは、私たちの心を豊かにする時間が不足しているからなのかもしれない。皆は休日に自身の過去を振り返って俯瞰したことはあるだろうか?そうすればきっと、私達がこれから生きていくために必要な原動力と未来に向けた夢や希望がはっきりと見て来るだろう。TWSのモットーは「技術の前に人ありき」である。その為に私はこれからも、様々な哲学をサプリメントにしていきたい。