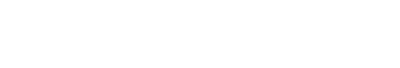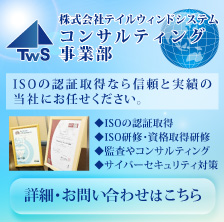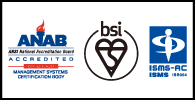先日、初めて海外旅行に行った。海外は言葉も通じず、怖い人が多いイメージがあり不安が大きかった。現地に到着してから、空港から宿泊先まで送迎車を手配していたのだが、予定時間になってもドライバーが現れず、困っていたところ、日本語が話せる別のドライバーさんが声をかけてくれた。事情を話すとすぐに電話で確認してくださり、お陰で担当ドライバーさんと合流することができた。助けていただいた方は現地ガイドだとのことで、その後もお勧めの場所を教えていただいたり、最終日には1日ガイドをお願いし、最高の1日を過ごすことが出来た。他にも、夕飯を食べ終えてからコンビニに向かったところ、突然日本語で声をかけられた。遅い時間だったこともあり警戒していたのだが、旦那と話が弾んで、私たちが翌日に行こうとしていたコーヒーショップに知り合いがいるので、今すぐ一緒に行かないかと誘われた。半信半疑の気持ちだったが、思い切ってお願いしたところ、お店の人も日本語が話せた為、会話が弾み、お目当てだったコーヒーを楽しみながら買うことができた。このような出来事から感じたことは、人に親切にすることでお互い良い気分になり、繋がりも増えることだ。私が抱いていた不安も、親切な人たちとの出会いで吹き飛び、楽しい一生の思い出とすることが出来た。私も今後、他人への親切な心を大切にし、その方を幸せな気分にすることが出来たら幸いだ。
- 2024/07/18