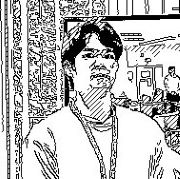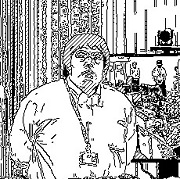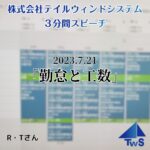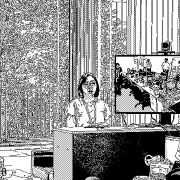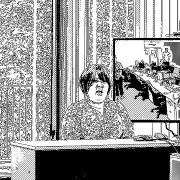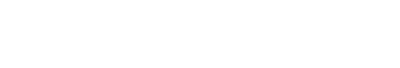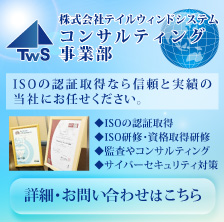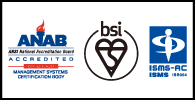我々が普段何気なく摂取している人工甘味料について考えたことがあるだろうか。人工甘味料にも種類がいくつかあるが、特によく知られているのはアスパルテームだろう。1980年代以降に広まり、砂糖の200倍の甘さがある非糖質の甘味料で、ゼロコーラや菓子など、多くのものに使用されている。糖質をOFFしたい人にとっては夢のような物質だが、それが先日WHOが発がん性物質としてIARCグループ2Bに分類されたことで話題になった。プロテインメーカー等ではアスパルテームを使用した商品の販売を停止した企業もあるが、私はアスパルテームが発がん性物質として認められたという事実より、この情報を今後どのように自分自身の食生活に活かしてていくかという事の方が重要だと考える。そもそも少量のアスパルテームより大量の砂糖の方が健康被害は大きく、IARCグループも2Bより上のグループが二つある。つまりアスパルテームを避ける=発癌のリスクを下げるにはならない。情報の表面だけを汲み、自身の行動に反映するのは危険であり、情報の本質を捉え、活かしていくことが現代の情報社会において重要だと再認識した。