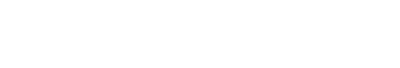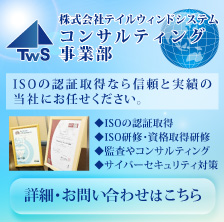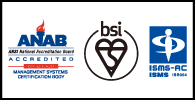私は生まれてから高校を卒業するまでの18年間、地方の実家で暮らしてきた。高校を卒業し、都内の大学に進学が決まったため、そこから初めての一人暮らしをすることとなった。私の両親は、学費やアパートの家賃の支払いに加え、毎月仕送りとしてお金を銀行口座に振り込んでくれた為、アルバイト等をほとんどしなくても十分に暮らすことが出来た。引越しの際にも車を出したり、荷物を詰めたりと全て手伝ってくれた。また、一人暮らしの私を心配して頻繁に会いに来てくれたり、連絡を取ることも多かった為、あまり一人暮らしでの辛さのようなものは感じずに学生生活を終えることが出来た。そして今、社会人になり自分で稼いだお金をもって、本当の意味で自立して生活できるようになった。今までずっと両親に助けられて生きてきた為、これからは両親に心配をかけないように、しっかりとした社会人生活を送っていきたい。そして感謝を忘れず、少しずつでも恩を返していきたい。