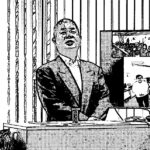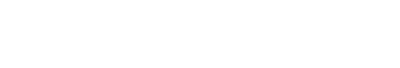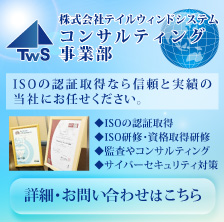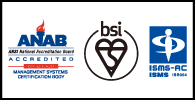本日は、ふるさと納税の申請期限日だが、皆は申請を済ませただろうか。私は一昨年からふるさと納税を始めたが、返礼品のサイトを眺めているだけでも、日本各地の名産品を知ることができるのが楽しい。このように、ふるさと納税と同じく、年末年始の過ごし方や食文化も地域や家庭ごとに大きく異なる。私は横浜で生まれ育ち、年越しの際は、船の汽笛を聞いてから寝るのが子供の頃の恒例行事だった。また、我が家のお雑煮は醤油ベースで、たっぷりの野菜と鶏肉が入っているのが当たり前だった。しかし、嫁ぎ先では除夜の鐘を聞きながら神社に初詣に出かける習慣があり、お雑煮もシンプルで、お澄ましに餅が入ったものだった。これには驚いたが、同時に「自分にとっての当たり前」が他の人にとってはそうでないことを実感した。このような「当たり前」の違いについて、全社員研修で研修を受けたことは記憶に新しい。人とコミュニケーションを取る際、前提条件を共有しないと話がかみ合わないことが多い。この違いは、仕事においては致命的な結果を招くこともあるため、注意が必要だ。しかし、プライベートにおいては、人との違いを理解し、許容したり気遣ったりすることが「思いやり」であり、さらにその違いを楽しめる心の広さや余裕を持ちたいと考えている。