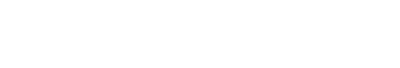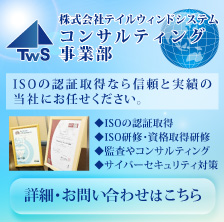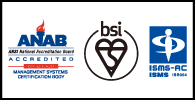本日はいわゆる年度末であり、明日から新生活が始まる人も多いだろう。年末とは暦年の12月31日であり、師走と言われるように忙しいと感じる人も多い。しかし、この年度末には色々な種類が有り、国や地方自治体の「会計年度」、学校の「学校年度」、企業の「事業年度」等がある。日本は殆どが4月1日から3月31日を年度にしている。事業年度を3月決算にしている企業が多い理由として、会計年度・学校年度・税制改正に合わせているからだ。期の途中に税制が変更になると手間がかかることや、新入社員が4月に入社する事を考慮してのことだろう。申告法人の20%は3月決算であるが、日経平均株価銘柄225社については、80%以上が3月末であり、12月末が10%である。つまり、年末での忙しさよりもこの3月31日の方が忙しいという人は多いのかも知れない。ただ世界的には、1月1日から12月31日を「会計年度」「事業年度」にしている国が多いそうだ。「学校年度」については殆どの国が9月をスタート月にしている。日本と同様に「会計年度」「事業年度」「学校年度」を4月スタートにしている国はインド等、数か国しかない。当社は12月決算であるが、とは言え明日からは新入社員も入社して、フレッシュな顔ぶれを見ることが出来る。私も昨年の4月に入社して一年が経過し、新たな気持ちで業務を遂行して行く。